衣類や空間の消臭・除菌に欠かせない花王の「リセッシュ」。しかし、使い終わった後の「リセッシュの捨て方」について、迷ったことはありませんか?スプレー缶のガス抜き、中身の処理、プラスチックボトルの分別など、間違った方法で捨てると事故や環境問題につながる恐れがあります。
この記事では、リセッシュを安全かつ環境に配慮して処分するための具体的な手順と、知っておくべき自治体の分別ルールを詳しく解説します。
リセッシュを捨てる前に知っておきたい基礎知識
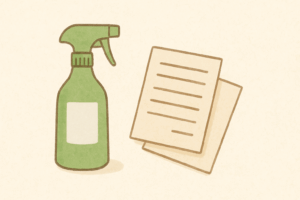
リセッシュを安全に捨てるためには、まず製品の性質を正しく理解しておくことが重要です。主要な成分やファブリーズとの違いを知ることで、中身の安全な処理方法が見えてきます。
リセッシュとは?種類と特徴
リセッシュは、花王が販売する衣類・布製品・空間用消臭剤のブランド名です。主な目的は、気になるニオイを元から消臭し、除菌すること。ラインナップは多岐にわたり、「除菌EX」「消臭ストロング」「アロマチャージ」など、用途や香りの有無によって選べます。
多くはトリガー式のスプレーボトルやエアゾール式のスプレー缶で提供されていますが、中身の主要成分は植物由来の消臭成分や除菌剤が中心です。種類によってアルコールの含有量が異なる場合があるため、火気への注意や中身の処理方法を考える上で、この違いを理解しておくことが安全な処分に繋がります。
ファブリーズとの違い
リセッシュの競合製品としてP&Gの「ファブリーズ」が有名です。どちらも衣類や布製品の消臭・除菌を目的としていますが、最大の違いは消臭成分の仕組みにあります。ファブリーズは環状オリゴ糖(サイクロデキストリン)という成分でニオイを包み込んで消臭するのに対し、リセッシュは緑茶エキスなどの植物由来の消臭成分がニオイの原因物質に作用して消臭するメカニズムを採用しています(※製品によって成分は異なります)。
中身の成分が異なっても、アルコール類を含む製品の場合は、中身の処理方法や火気の近くでの作業には十分な注意が必要です。どちらの製品もスプレータイプで容器の構造は似ているため、容器の捨て方(ガス抜きなど)に関する基本的な注意点は共通しています。
主な成分と注意点
リセッシュの多くの製品に含まれる主な成分は、「両性界面活性剤」「緑茶エキス」「除菌剤」「エタノール(アルコール)」などです。特に注意したいのが「エタノール」や「アルコール」が含まれている製品です。アルコールは引火性があるため、中身を大量に捨てる際は、火気の近くでの作業は厳禁です。
また、誤って飲用した場合や目に入った場合は危険ですので、中身の処理中は換気を良くし、お子様やペットが近づかない場所で行ってください。製品の裏面に記載されている「成分」や「使用上の注意」を確認し、内容物を理解しておくことで、捨て方の安全性が格段にアップします。
リセッシュの中身を安全に捨てる方法

リセッシュを捨てる際、中身が残っていると、そのままゴミ袋に入れることはできません。引火や液漏れを防ぎ、環境への負荷を減らすためにも、残った中身は正しく安全に処理しましょう。
中身が残った時の正しい処理手順
リセッシュの中身が残っている場合、まずは「使い切る」のが最も推奨される方法です。しかし、それが困難な場合は、以下の手順で処理します。
- 換気の良い、火気のない屋外またはベランダなどの場所を選びます。
- スプレーのノズル(トリガー)を外し、液体を広口の容器(バケツなど)に移します。エアゾール缶の場合は、後述のガス抜きを行いながら中身を出します。
- 取り出した液体は、新聞紙や古布、ティッシュペーパーなどに染み込ませて、燃えるゴミとして処分します。
- 容器は空にしてから、自治体の分別ルールに従って処分します。
この際は、液体が手につかないようにゴム手袋などを着用し、作業中は火気を避けるようにしてください。
新聞紙・ティッシュで吸わせる方法
液体状の洗剤や消臭剤を捨てる際の最も一般的な方法は、新聞紙やティッシュペーパー、いらない布などに吸わせて可燃ゴミとして出すことです。この方法は、液体の飛散や下水管への負荷を防ぐ点で推奨されます。
| ステップ | 具体的な手順 |
|---|---|
| 準備 | 大きなビニール袋、新聞紙(または古布)、ゴム手袋を用意 |
| 吸い込ませる | ビニール袋の中に新聞紙を広げ、リセッシュの液体をゆっくりと新聞紙全体に染み込ませる |
| 処分 | 液体を吸った新聞紙をビニール袋の口をしっかり縛り、「燃えるゴミ」として分別する |
一度に大量に吸わせると液漏れの原因になるため、何度かに分けて作業しましょう。また、ビニール袋の中で作業することで、周囲を汚すリスクを減らせます。
下水に流していいケース・ダメなケース
リセッシュのような消臭・除菌スプレーの成分は、少量であれば基本的に問題ないとされていますが、大量に下水に流すのは避けるべきです。家庭用の排水システムや環境への負荷を考慮すると、推奨される捨て方ではありません。
- 【ダメなケース】
- 残量が半分以上など、大量の液体を一気に流す。
- アルコール濃度が高い製品を流す(下水管内のバクテリアに悪影響を与える可能性がある)。
- 【流しても比較的安全なケース(少量・例外)】
- バケツなどに水を大量に入れ、そこに少量ずつ薄めながら流す(※基本的には推奨せず、新聞紙処理を優先)。
結論として、環境保護と安全性の観点から、リセッシュの中身は新聞紙や古布に吸わせて「燃えるゴミ」として処分する方法を強くおすすめします。
スプレー缶・ボトルの正しい処分法

中身を空にした後のスプレー缶やプラスチックボトルも、分別ルールに従って正しく処分する必要があります。特にスプレー缶は、残ったガスが原因で火災につながる危険があるため、細心の注意が必要です。
スプレー缶のガス抜きと注意点
エアゾールタイプのリセッシュ(スプレー缶)を捨てる際は、必ず「中身を完全に使い切り」「ガスを抜く」作業が必要です。ガス抜きが不十分だと、収集車や処理施設での爆発・火災事故の原因になります。
- 完全に使い切る: 振っても音がしなくなるまでボタンを押し続けます。
- 安全な場所で行う: 換気が良く、火の気がない屋外で、風通しの良い場所を選びます。
- ガス抜きを行う: 多くの製品には、残ガス排出用の「ガス抜きキャップ」がついています。製品裏面の指示に従い、キャップや専用器具を使ってガスを完全に排出します。
- 穴を開けない: 原則、穴開けは不要(次項参照)です。
作業中は静電気が起きにくい服装を選び、長時間の連続噴射は避けてください。ガス抜きができない場合は、無理せずメーカーや自治体に相談しましょう。
穴を開けるべき?自治体ごとの違い
以前はスプレー缶に穴を開けてから捨てるのが一般的でしたが、現在は、多くの自治体で穴開けが不要、あるいは禁止されています。穴開け時に引火して火傷や火災事故が発生するリスクが高いためです。
- 穴開け不要(推奨)の自治体:
- 中身を完全に使い切り、ガス抜きをすれば、そのまま「資源ゴミ」または「不燃ゴミ」として回収。
- 穴開けが必要な自治体(少数派):
- 必ず指定された場所(屋外、火気厳禁)で、指定された工具を使って穴を開ける必要があります。
判断に迷ったら、必ずお住まいの自治体のホームページで「スプレー缶・カセットボンベの捨て方」を確認してください。誤った処分方法は、重大な事故につながります。
プラ容器・詰め替えパウチの分別ルール
エアゾール缶ではないトリガー式のプラスチックボトルや、詰め替え用のパウチ容器は、「プラスチック製容器包装」として分別するのが一般的です。
- プラスチックボトル:
- 中身を空にし、軽く水洗いする。
- トリガー部分やキャップは分別が異なる場合がある(例: 本体は「プラ」、トリガーは「燃えるゴミ」)。自治体ルールを確認。
- 「プラスチック製容器包装」の日に出す。
- 詰め替えパウチ:
- 中身を空にし、軽く水洗いする。
- 「プラスチック製容器包装」の日に出す。
どちらも、汚れが落ちない場合は「燃えるゴミ」になる自治体もあるため、注意が必要です。容器に記載されているプラマーク(♷)を確認しましょう。
捨てる時に気をつけたい自治体ルール

リセッシュの捨て方は、住んでいる地域によって大きく異なります。安全に処分し、スムーズに回収してもらうためにも、お住まいの地域の分別ルールを正しく把握しておきましょう。
燃えるゴミ・資源ゴミの分け方
リセッシュ関連のゴミの分別は、主に以下の3パターンに分かれますが、自治体によって定義が異なります。
| ゴミの種類 | 一般的な分別 | 注意点 |
|---|---|---|
| 中身(液体を吸わせた紙など) | 燃えるゴミ(可燃ゴミ) | しっかり密閉し、液体が漏れないようにする。 |
| スプレー缶(エアゾール缶) | 資源ゴミ、または不燃ゴミ(※穴開け不要が増加) | 必ず完全にガス抜きを行う。他の缶と袋を分ける指定がある場合も。 |
| プラスチックボトル・パウチ | プラスチック製容器包装(資源ゴミ) | 中身をきれいに洗い、汚れを落とす。 |
「資源ゴミ」に含まれるか、「不燃ゴミ」に含まれるかの違いは、自治体の処理施設の方針によるため、必ず確認が必要です。
自治体別の問い合わせ・確認ポイント
正しい捨て方を知るための最も確実な方法は、お住まいの自治体の情報を直接確認することです。特にスプレー缶の扱いは地域差が大きいため、以下のポイントを参考に確認しましょう。
- 【確認ポイント】
- スプレー缶の穴開けは必要か?(例: 東京都23区の多くは穴開け不要)
- スプレー缶は何ゴミか?(例: 横浜市は「燃やすゴミ」とは別で「スプレー缶」として収集。名古屋市は「不燃ごみ」)
- プラスチックボトルやトリガー部分の分別区分は?
- 中身が残った場合の特別収集があるか?
ホームページで「〇〇市 ごみ分別」「スプレー缶 捨て方」と検索するのが最も手軽です。地域別の例として、名古屋市や横浜市のように、中身が残ったスプレー缶は危険物として特別に扱われる場合があることを覚えておきましょう。
環境に優しい処分と再利用のアイデア

リセッシュを捨てるだけでなく、環境に優しい方法で活用したり、購入段階からゴミを減らす工夫をすることも大切です。最後まで責任を持って利用し、環境負荷を減らしましょう。
残り香を掃除や脱臭に活かす方法
リセッシュのボトルに中身がごく少量だけ残ってしまった場合、無理に捨てずに掃除や脱臭に活用するアイデアがあります。特に香りのついたタイプであれば、最後まで有効活用できます。
- 床拭き掃除に利用: バケツの拭き掃除用の水に、残ったリセッシュを数滴混ぜて、床や壁を拭くのに利用します。ほのかな香りが残り、部屋全体がさわやかになります。
- ゴミ箱の脱臭に: 少量のリセッシュを、ゴミ箱の底に敷く新聞紙やティッシュに吹きかけてから使うと、ゴミの嫌なニオイを軽減できます。
- 拭き取り用スプレーとして: トイレや玄関マットなどのニオイが気になるところに、スプレーとして最後の1滴まで使い切るようにしましょう。
これらの方法で「使い切る」ことができれば、液体を新聞紙に吸わせる手間も省け、環境にも優しい処分になります。
詰め替え用を活用してごみを減らす工夫
リセッシュは多くの製品で詰め替え用パウチが販売されています。本体ボトルを捨てずに繰り返し使用することは、プラスチックごみの削減に直結する最も手軽で効果的な環境対策です。
- 本体ボトルを大切にする: 本体ボトルは耐久性があり、何度でも使えます。汚れたら軽く洗うなどして、長く使用することを心がけましょう。
- 詰め替えパウチの選び方: 大容量の詰め替えパックを選ぶことで、使用するパウチの枚数を減らすことができます。
- パウチの処理: 詰め替えパウチは、前述の通り中身を空にして軽く水洗いすれば「プラスチック製容器包装」として資源化されます。
リセッシュを使い切るサイクルの中で、詰め替えを習慣化することは、地球環境に対する小さな貢献になります。
安全な保管と整理のコツ
リセッシュを安全に使い切り、スムーズに処分するためには、日頃の保管方法も重要です。適切な場所に保管することで、事故や劣化を防ぐことができます。
- 火気厳禁: 特にアルコールを含むスプレー缶・ボトルは、ストーブやコンロ、直射日光の当たる場所(車内など)を避けて保管します。
- 子どもの手の届かない場所へ: 誤飲・誤噴射を防ぐため、ロック機能(トリガー式の場合)を活用し、棚の上など子どもの手が届かない場所に保管しましょう。
- 残量確認: 処分が必要になる前に残量を把握するため、残量が少なくなったら棚の手前など目につく場所に移動させて、早く使い切るように意識しましょう。
整理整頓された場所で、正しく保管することで、安全に使い切るまでの期間を延ばすことができます。
まとめ

この記事では、リセッシュの中身・スプレー缶・プラスチックボトルの安全で環境に優しい捨て方を詳しく解説しました。
リセッシュの処分で最も重要なポイントは、以下の3点です。
- 中身は新聞紙などに吸わせて燃えるゴミへ。下水には流さない。
- スプレー缶は換気の良い屋外で完全にガス抜きを行う(穴開けは自治体ルール確認)。
- プラスチック容器・パウチは洗浄して「プラスチック製容器包装」へ。
リセッシュを正しく処分することは、ご家庭の安全を守り、地域社会の環境保全にも繋がります。お住まいの自治体のルールを今一度確認し、気持ちよく安全にリセッシュを処分しましょう。


