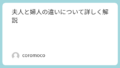「草かんむりに鳥」と書くちょっと珍しい漢字「蔦」。
普段の生活ではあまり意識されないかもしれませんが、実は身近なところでよく見かける植物の名前です。たとえば、古い校舎の壁や甲子園球場、大学のキャンパスなど、建物の外壁に美しく絡みついているあの植物――それが「蔦(つた)」なのです。
この記事では、「蔦」という漢字の基本的な読み方や意味、成り立ちと由来、植物としての特徴、環境対策としての現代的な活用例、さらには人名や苗字としての使用例まで、深掘りして分かりやすくご紹介していきます。
「蔦」の読み方と意味を正しく知ろう

まずは「蔦」の基本から押さえていきましょう。
この漢字の読み方は以下の通りです
- 音読み:チョウ
- 訓読み:つた
「つた」という読み方は中国語には存在しない、日本語特有の読み方です。
「蔦」という漢字には大きく分けて2つの意味があります。
1つは、「ヤドリギのように他の植物に寄生して生える植物の総称」。
たとえば、カシワやヤナギ、クワなどの木に寄生する「槲寄生(コクキセイ)」や「桑寄生(ソウキセイ)」などがあります。
もう1つは、「つる性の植物全般」。
特に日本ではブドウ科の「ナツヅタ(夏蔦)」を指すことが多く、校舎の外壁や甲子園球場の壁などでよく見られるのがこの植物です。
また、キヅタ(木蔦)やツタウルシなども、同じく「蔦」に含まれるつる性木本(もくほん)です。
なぜ草かんむりに「鳥」?漢字の成り立ちと語源に迫る!
「蔦」という字の構成は、植物を意味する「艹(草かんむり)」と、「鳥」の2つの要素から成り立っています。
このような漢字は「形声文字(けいせいもじ)」と呼ばれ、意味と音を組み合わせて作られています。
では、なぜ「鳥」が含まれているのでしょうか?
それは、鳥が枝にとまっているように、「蔦」も木や壁に絡みついて生きている様子を表現しているからだとされています。
自然界の動きと植物の生態をうまく漢字で表現している、非常に美しい発想ですね。
ちなみに、「つた」という言葉の語源は古語の「つたふ(伝ふ)」に由来します。
他のものに伝ってのぼるという植物の性質をうまく言い表していて、江戸時代の語源辞典『和句解』にもその記録が残っています。
植物としての「蔦」の魅力とは?見た目だけじゃない実力派!

蔦と聞くと、外壁に絡む見た目の美しい植物というイメージが強いかもしれません。
しかし、蔦にはそれ以上の実用的な価値がたくさんあります。
蔦の形態的特徴
- 葉は3つに裂けており、縁は鋸歯(きょし:ギザギザ)状
- 若い茎には3小葉、成熟すると1枚の葉が3中裂に変化
- 茎は木のように硬くなり、直径4cm以上になることも
- 花は小さく黄緑色(3~4mm)で、5本の雄しべと1本の雌しべを持つ
- 実は黒紫色の球状の液果で、熟すとつややかになる
- 壁に貼りつくための「吸盤」を持ち、岩や外壁に強く付着する
自然のエアコンとしての効果
- 夏の直射日光を遮ることで室温の上昇を防ぐ
- 葉の水分が蒸発することで気化熱が発生し、周囲を冷やす効果
- 冬は葉が落ちるため、太陽光を取り入れやすくなり、暖房効率も向上
✅このように、蔦は「見た目」だけでなく、エコロジー建築や省エネ対策としても非常に優秀な植物なのです。
蔦を活用したエコ建築の取り組み
近年、温暖化対策やヒートアイランド現象の抑制として、建物の外壁を植物で覆う「壁面緑化」が注目されています。
東京都内オフィスビルの例
- 自動散水機能付きの蔦の壁面を導入
- 夏の冷房費が約20%削減
- ビル周辺の体感気温が平均1.5度下がる効果も
神奈川県の集合住宅での試み
- ベランダに蔦を設置し「グリーンカーテン」として利用
- 電気代が月平均15%削減
- 居住者の環境意識も向上
商業施設(大阪市)での導入
- 蔦を用いた景観デザインで、施設の印象が向上
- 来場者の滞在時間が増加し、売上にも好影響
- 冬場は暖かい日差しを取り込み、省エネにも貢献
✅このように「蔦」は、省エネ・環境対策・美観の向上と、まさに一石三鳥の効果を持つ“未来型植物”として再評価されています。
「蔦」は名前や苗字にも使える?意外な人名例を紹介!
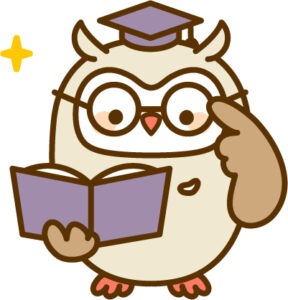
「蔦」は人名用漢字としても登録されており、苗字や家紋などに幅広く使われています。
日本全国にいる「蔦」さんの分布
- 大阪府:約200人
- 広島県:約130人
- 東京都・北海道:約100人
- 兵庫県:約90人
合計で約1,400人が「蔦」という姓を持っていると言われています。
「蔦」を含む珍しい苗字のバリエーション
- 蔦谷(つたや・つたたに)
- 蔦井(つたい)
- 蔦浦(つたうら)
- 蔦木(つたき)
- 蔦尾(つたお)
- 蔦垣(つたがき)
- 蔦壁(つたかべ)
- 大蔦(おおつた)
- 岡蔦(おかじま)←珍読み
- 笠蔦(かさじま)←こちらもユニークな読み方
また、「鳥」をつくりに含む漢字は珍しく、蔦以外には「嶋(しま)」「嶌(しま)」「樢(くぬぎ)」などわずかしか存在しません。
一方、部首として使われる例は「鳳(ほう)」「鶴(つる)」「鷹(たか)」など多数あります。
【まとめ】蔦は美しさ・知恵・未来をつなぐ日本の宝

「蔦(つた)」という漢字には、植物のたくましさと、日本人の美意識、そして未来への可能性が詰まっています。
外壁を彩る美しい蔦は、見た目だけでなく、地球にもやさしい存在です。
そしてその漢字の中には、「自然と共に生きる」という、私たちの暮らし方へのヒントが込められているのかもしれません。
街で蔦を見かけたとき、ちょっと立ち止まって、「この植物、すごい力を秘めてるんだな」と思い出してもらえたらうれしいです。