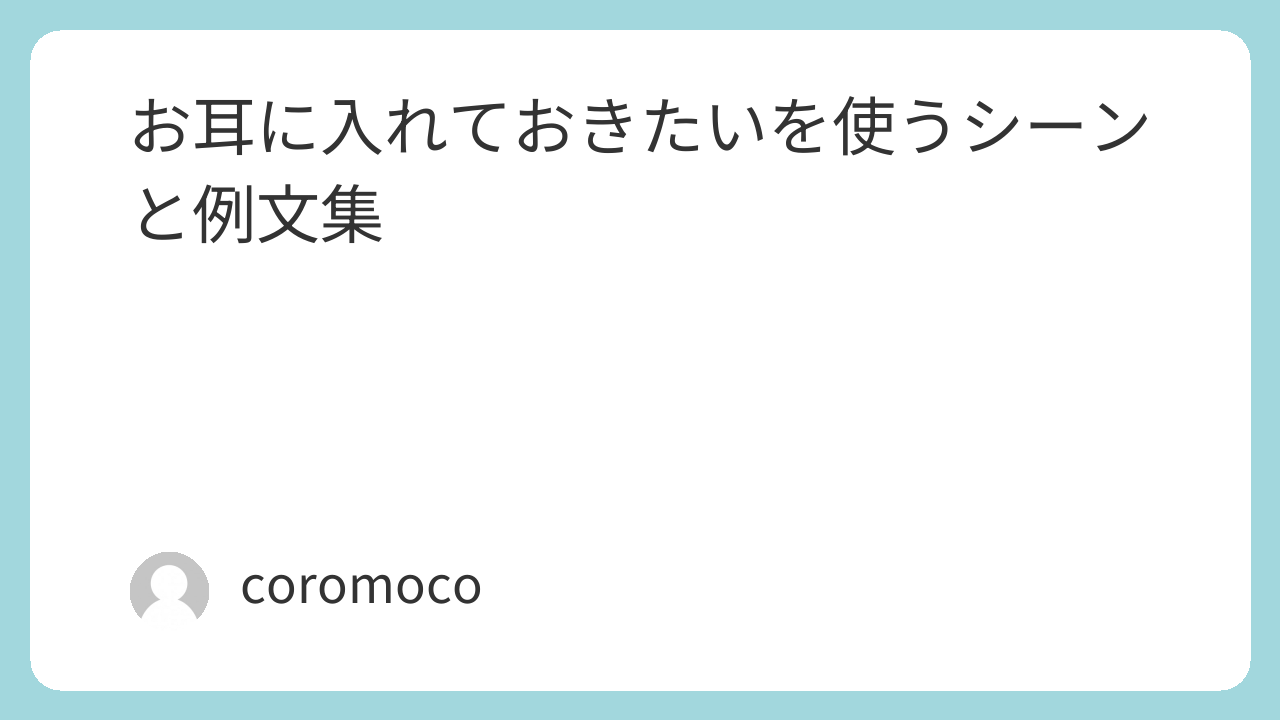日常会話やビジネスシーンで、相手に丁寧に情報を伝える言い回しとして使われる「お耳に入れておきたい」。この表現には、控えめでありながら相手への配慮を込めた日本語独特の美しさがあります。
本記事では、「お耳に入れておきたい」の意味や使い方をわかりやすく解説し、具体的な例文や類語、注意点も併せてご紹介します。適切に使いこなせば、より丁寧で信頼感のあるコミュニケーションが実現できます。
「お耳に入れておきたい」の意味と使用法

まずは「お耳に入れておきたい」の基本的な意味と、敬語としての役割について確認しておきましょう。
「お耳に入れておきたい」とは?
「お耳に入れておきたい」は、相手に何か情報や報告事項を丁寧に伝えるときの表現です。この表現には、単に伝えるという行為にとどまらず、相手への配慮や敬意、そして控えめな姿勢を示す日本語特有の美意識が込められています。
✅ 「お伝えしたい」や「知っておいていただきたい」といった意味合いを、やや遠回しで控えめに表現する言葉です。
そのため、情報を押しつけることなく、自然な流れで相手に伝えることができるのも、この言い回しの利点です。
特に目上の人や取引先など、敬意を払いたい相手に使うのが一般的です。また、ビジネスシーンに限らず、かしこまったフォーマルな場面でも適切に使用できます。
敬語と謙譲語の違い
この表現は、謙譲語に分類されます。
| 種類 | 例 | 使う対象 |
|---|---|---|
| 尊敬語 | おっしゃる、なさる | 目上の人の行動を高める |
| 謙譲語 | お耳に入れる、申し上げる | 自分の行動をへりくだる |
| 丁寧語 | です・ます | 一般的な丁寧な表現 |
✅ 「お耳に入れておきたい」は、自分の行為(伝える)をへりくだる形で、相手への丁寧な配慮を示します。
ビジネスシーンでの基本的な使い方
ビジネスでは、「少し気になる点がある」「予め知っておいていただきたいことがある」といった状況で使われます。このような場面では、相手にプレッシャーを与えることなく、情報を丁寧に共有する意図が求められます。
「お耳に入れておきたい」という表現を使うことで、状況を軽やかに伝えつつも、重要性のある情報であることをさりげなく示すことができます。
たとえば、上司やプロジェクト関係者にリスク情報や進捗の変更を共有する際など、相手の判断材料として有益な内容に使うと効果的です。また、直接の対応を求めない場合や、今後の判断に備えて把握しておいてほしい内容を共有する際にも適しています。
例:
本件について、念のためお耳に入れておきたいことがございます。
✅ あくまで控えめな表現なので、指示や依頼ではなく“共有”を目的とした文脈で使うのが適切です。
そのため、相手の行動を促すというよりは「知っておいていただけると助かります」といったニュアンスになります。
「お耳に入れておきたい」を使うシーン

では、具体的にどんな場面で使うと効果的なのでしょうか? 以下に代表的なシーンを挙げてみましょう。
上司への報告のタイミング
上司に対して事前に知っておいてもらいたいことがあるときに活躍する表現です。特に、トラブルの予兆や顧客からの反応、進行中のプロジェクトに関する軽微な変更点など、すぐに対応を求めるわけではないが、「念のため共有しておくべきこと」に適しています。
この表現を使うことで、報告のトーンが柔らかくなり、上司にもストレスなく情報を届けられるという利点があります。急な割り込み感を与えず、相手の時間や状況に配慮して伝えることができるため、信頼関係の構築にも寄与します。
例:
今朝の会議について、少々お耳に入れておきたい点がございます。
✅ 相手の都合を考慮しながら、自然に会話へ入ることができます。
取引先とのコミュニケーションでの活用
丁寧さが求められる取引先への情報共有にも有効です。新商品に関する補足事項や、納品スケジュールの微調整など、あえて「正式な案内」ではなく、非公式の情報として伝えるニュアンスを持たせたいときに効果的です。
この言い回しを使えば、相手にプレッシャーを与えずにスムーズな関係性を保つことができます。また、ちょっとした懸念事項や背景事情を共有する際にも役立ちます。
例:
ご参考までにお耳に入れておきたい内容がございます。
✅ 「お知らせいたします」よりも柔らかく、相手に配慮した印象を与えられます。
社内会議での表現例
会議中、補足情報を伝えるときや、決定に影響しうる情報を共有したいときにも使えます。議論の流れを止めずに、別視点からの情報提供や注意喚起がしたいときにも便利な表現です。
また、デリケートな情報を共有する際にもこの言い回しを用いることで、相手に受け入れられやすい柔らかいトーンで発言することができます。
例:
今後の進行に関わる件として、お耳に入れておきたいことが一つございます。
✅ 会議の流れを妨げずに、注意を促す役割も果たします。
「お耳に入れておきたい」の類語と言い換え

類語を知っておくことで、言い回しにバリエーションを持たせることができます。
| 表現 | ニュアンス |
|---|---|
| お伝えしておきたい | 一般的でわかりやすい |
| ご参考までに | カジュアル寄りで情報提供目的 |
| 念のため共有させていただきます | 注意喚起やリスクを示唆したい時 |
| 一言申し上げます | ややフォーマル、やや堅い |
✅ 場面に応じて表現を使い分けると、より柔軟な対応が可能になります。
ビジネスメールにおける効果的な活用法

ビジネスメールでは、口頭よりも慎重な言葉選びが必要です。「お耳に入れておきたい」は、相手に押し付けがましくなく情報を伝えたいときにぴったりです。
メールでの正しいタイミング
例えば、報告書の送付時や事前の注意喚起などに活用できます。特に、文面でのやり取りは相手の都合を配慮するうえでも「お耳に入れておきたい」というフレーズが効果的に働きます。口頭での報告が難しい場合や、あくまで軽く共有しておきたい内容がある場合には、この表現を使うことで控えめかつ丁寧な印象を与えることができます。
また、リスク要因や進行中の調整事項など、強調しすぎたくないが知らせておいた方が良い事項にも向いています。受け取る側に「押しつけられている」印象を与えず、スムーズな情報共有を可能にします。
例:
別件となりますが、お耳に入れておきたいことがございます。 本件は正式決定前ですが、事前にご承知おきいただけますと幸いです。
必要な情報の共有方法
・段落を分けて簡潔に書くことで、読み手が情報の整理をしやすくなり、視認性も高まります。特にメール本文では、要点ごとに空白行を挟むなどの工夫が有効です。
・「重要ではないが把握しておいてほしい内容」であることを明示することで、受け手の心理的負担を軽減し、柔らかい印象で伝えることができます。
・主文と混在しないよう注意することにより、本文の主旨を明確に保つことができ、補足情報や背景説明などは別段落にすることで、読みやすさと説得力が向上します。
印象を良くする言い回し
- 「念のため」や「差し支えなければ」などを添えると、柔らかい印象になります。これにより、相手が構えず自然に受け止められる雰囲気を作ることができ、情報提供がよりスムーズになります。また、文面上で相手に対する配慮をしっかりと示すことができるため、印象が格段に良くなります。
- 結びに「ご参考までにご確認いただけますと幸いです」や「お忙しいところ恐縮ですが、ご一読いただけますと幸いです」などを添えると丁寧です。こうした一言を加えることで、メール全体のトーンが和らぎ、より信頼感のあるやり取りにつながります。
「お耳に入れておきたい」の利用に関する注意点

・相手の立場によっては、かえって堅苦しく感じられることもあるため、親しい同僚やフラットな会話では使いすぎないのがポイントです。特にカジュアルな社内チャットや雑談ベースのやりとりでは、やや形式的すぎる印象を与えてしまうことがあるため、使う場面は慎重に見極める必要があります。相手との関係性やその場の雰囲気に合わせて、もっと柔らかい表現や日常的な言い回しを選ぶことで、より自然なコミュニケーションが可能になります。
・相手が忙しいタイミングでは、「今少しよろしいでしょうか」といった前置きを加えることで、自然に切り出せます。さらに、「お時間を取らせてしまって申し訳ありませんが」や「一言だけご報告させてください」などのクッション言葉を添えることで、相手の負担を和らげつつ、スムーズな会話の導入が可能です。こうした配慮が、円滑なやり取りの鍵となります。
「お耳に入れておきたい」の具体的な例文

ビジネスシーンの例
明日の商談に関連して、お耳に入れておきたい事項がございます。
ご多忙とは存じますが、ご確認いただけますと幸いです。
また、先方の希望内容に一部変更が加わる可能性もございますため、念のため共有させていただきます。
カジュアルシーンでの例
ちょっとお耳に入れておきたいことがあるんだけど……
来週の予定、変更になるかもしれないよ。
もしかしたらクライアントの都合で会議がずれ込むかもって話が出てるの。
正式な連絡はまだだけど、念のため頭に入れておいてね。
フォーマルな場面での例
大変恐れ入りますが、一点お耳に入れておきたい件がございます。
後ほどお時間をいただけますでしょうか。
可能であれば10分ほど、お話しする機会をいただけると幸いです。
内容は今後の進行にも関わるため、念のためご確認をお願い申し上げます。
「お耳に入れておきたい」と他の敬語との違い

この表現は、単に情報を伝えるだけでなく、相手への気配りや礼儀を伴った“知らせ”の形です。単なる報告ではなく、「あなたのために、あらかじめ知っておいていただきたい」といった思いやりや配慮が込められているのが特徴です。
たとえば「言っておきたい」ではストレートすぎて柔らかさに欠けますし、「ご報告申し上げます」ではかしこまりすぎる印象になりがちで、日常のやり取りや軽微な情報共有には重たく感じられることがあります。
一方で「お耳に入れておきたい」は、その中間の立ち位置にあり、適度な丁寧さと控えめなトーンが両立したバランスの良い言い回しです。また、相手が目上の方であっても、構えることなく自然に会話に取り入れられるのも大きなメリットです。
✅ その中間として、「お耳に入れておきたい」は非常にバランスの良い表現といえるでしょう。
状況に応じて、他の敬語と組み合わせて活用することで、より洗練されたコミュニケーションが可能になります。
【まとめ】
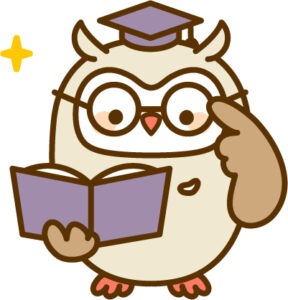
「お耳に入れておきたい」という表現は、ただの情報共有にとどまらず、相手への敬意と配慮を込めた日本語の奥ゆかしさが詰まった言い回しです。
ビジネスシーンからカジュアルな会話、フォーマルな場面まで幅広く活用できる表現ですが、使い方やタイミングを誤ると堅苦しく感じられてしまうこともあるため、場面や相手との関係性に応じた使い分けが大切です。
また、類語やメールでの表現、具体的な例文を参考にすることで、語彙力や表現の幅も広がり、コミュニケーションの質も向上します。
✅ 相手を思いやる気持ちを忘れず、柔らかく伝えたいときに「お耳に入れておきたい」をぜひ活用してみてくださいね。