マットレスの汚れや臭い、なんとかしたいけれど洗えないし、どうしていいか分からない……そんな悩みを持つ方も多いのではないでしょうか?とはいえ、毎日使うものだからこそ、清潔に保っておきたいですよね。そんなときに活躍するのが、家庭にある”重曹”を使えば、マットレスのお掃除が簡単にできるという手軽さ。今回は、重曹をふりかけるだけでできる掃除法から、臭いやカビ予防まで、やさしく解説していきますので、初めての方もぜひ参考にしてみてください。
重曹でマットレスをきれいに!その効果とは?
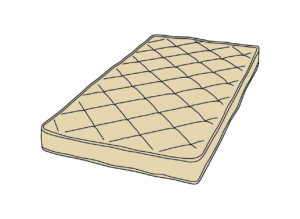
マットレスは毎日使うものだからこそ、知らないうちに汗や皮脂、汚れなどが蓄積していきます。さらに時間が経つと、それらが臭いやシミの原因になることも。重曹はその汚れや臭いをやさしく中和してくれる、頼れるお掃除アイテムです。
重曹の消臭効果とは?
重曹は弱アルカリ性で、酸性の臭い(汗や皮脂など)を中和し、においの元を吸着してくれる性質があります。これにより、臭いを根本から軽減できるとされており、寝具などの布製品に使っても安心です。
また、重曹は自然素材であるため、香料や化学成分を含む市販の消臭剤とは異なり、身体への刺激が少ないのもメリットのひとつです。香りでごまかすのではなく、臭い自体を取り除くことができる点で、ナチュラル志向の方にも人気があります。特に寝室など長時間過ごす空間では、やさしい使用感が好まれるでしょう。
マットレスにおける汚れや臭いの原因
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 汗・皮脂 | 毎晩の就寝中に自然に分泌され、マットレスの内部に染み込んで蓄積しやすい |
| ホコリ | 衣類や布団から舞い落ち、時間の経過とともに層になって衛生的にも影響を与える |
| ダニ | 繊維の奥に入り込みやすく、アレルギーの原因にもなりやすい |
| 食べこぼし等 | 小さなお子さんやペットがいるご家庭では特に注意が必要で、臭いや汚れの原因になることも |
| 湿気・結露など | 空気中の水分がマットレスに染み込み、カビや菌の温床になることがある |
重曹を使った具体的な掃除方法

「ただふりかけるだけ」で済むのが、重曹の魅力のひとつ。粉のまま使うだけで、気になる臭いや湿気をしっかり吸収してくれる頼もしさがあります。さらにスプレーを活用すれば、狙った箇所にピンポイントでアプローチでき、より手軽で便利になります。
重曹をふりかける基本方法
- マットレス全体に重曹を均一にふりかける(約100g程度。広げた新聞紙などの上で作業すると後片付けもラクになります)
- 30分〜1時間ほど放置(臭いや湿気を吸収。可能であれば日当たりや風通しのよい場所に置くとより効果的)
- 掃除機でしっかり吸い取る(残ると白い粉が服に付着するため丁寧に。細かいノズルを使うとすみずみまで吸い取れます)
重曹スプレーの作り方と使い方
材料
- 水:200ml(できれば常温の水)
- 重曹:小さじ1(食品用がおすすめ)
- お好みでアロマオイル1〜2滴(ラベンダーやティーツリーなど)
作り方&使い方
- スプレーボトルに材料を入れてよく振る(アロマオイルを入れる場合は最後に)
- 臭いの気になる箇所や、湿気が気になる部分に軽くスプレー
- 完全に乾くまで換気して放置し、使用後はスプレーボトルを冷暗所に保管する
効果的な掃除のタイミングと頻度
- 週1回のふりかけ掃除が理想的ですが、ペットや小さなお子さんがいるご家庭では、もう少し頻度を上げてもよいでしょう
- 季節の変わり目や梅雨・夏は頻度を増やすと清潔を保てます。特に湿度が高い時期は、湿気や臭いが発生しやすいため、こまめなケアがおすすめです。
マットレスの黄ばみや臭いを取り除くテクニック

日々の汗や突発的な汚れにも、重曹は大活躍。掃除が難しいマットレスにもやさしく使えるので、手軽に清潔をキープしたい方にぴったりです。ここでは具体的なトラブルに合わせた使い方をご紹介します。
突発的な汚れや汗じみの対処法
- まず水で軽く叩いて汚れを取る(ゴシゴシはNG。タオルなどで優しく押さえるようにして、水分と汚れを吸い取るのがポイントです)
- 重曹をふりかけて1時間ほど置く(広範囲の場合は重曹の量を多めにすると効果的です)
- 掃除機で吸い取る→陰干しで乾燥(風通しのよい場所で、できれば数時間以上しっかり乾かしましょう)
ペットの臭い対策と重曹の活用
- 臭いの強い箇所に多めに重曹をふりかける。特にペットの寝床に近い場所や粗相をしやすい箇所は念入りに。
- 必要に応じてスプレーも併用し、マットレス全体に優しくなじませるとより効果的です。
- 月2回以上の頻度でのお手入れがおすすめですが、換毛期や雨の日が続いた後などは少し頻度を増やすと清潔を保ちやすくなります。
マットレスの湿気予防と重曹の役割
- カビの原因である湿気を重曹が吸収。特にジメジメした季節や、通気性が悪くなりがちな冬場には、重曹の吸湿性がとても役立ちます。
- 湿気がこもりやすい寝室では定期的な換気とセットで使うのが◎。窓を開けて風を通したり、扇風機や除湿機を併用することで、重曹の効果をより引き出すことができます。
掃除の後に行うべきメンテナンス
重曹掃除だけでなく、その後のケアも大切です。マットレスを長く快適に使い続けるには、湿気をためない・清潔を保つための工夫が欠かせません。ここでは、掃除後に行っておくと効果的なアフターケアのポイントをおさえておきましょう。
換気の重要性とその方法
- 掃除後はマットレスを立てかけるか、風通しの良い場所に置く。湿気がたまりにくいよう、壁に直接つけずに少し隙間を空けて立てかけると効果的です。
- 窓を開けて空気の流れを作ることがポイント。晴れた日には2か所以上の窓を開けて対角線上に風が通るようにすることで、効率よく湿気を逃すことができます。また、扇風機やサーキュレーターを併用するとより短時間で効果が得られます。
布団やシーツの洗濯と陰干しの効果
- シーツやカバーは週1回の洗濯を推奨。肌に直接触れるものなので、こまめな洗濯が清潔さを保つポイントになります。
- 天日干しが難しい場合は陰干し+風通しの良い部屋でしっかり乾かしましょう。湿気を残さないよう、扇風機などを活用してしっかり乾燥させるとより効果的です。
- また、季節の変わり目や湿度の高い日が続く時期には、洗濯頻度をやや増やすことで清潔な寝具環境を維持しやすくなります。
消臭スプレーやファブリーズの併用法
- 重曹掃除と組み合わせるとさらに効果的。特に臭いが強く残っている場合や、来客前の仕上げとして使うと清潔感が高まります。
- 香り付きのスプレーは気分転換にもなりますが、人工的な香りが苦手な方は無香タイプを選ぶと安心です。
- 使用後は十分に換気を行い、スプレーが完全に乾くのを確認してからシーツやカバーを戻すとベタつきを防げます。
重曹以外の掃除方法とコスト comparison

実は重曹以外にも選択肢はあります。最近ではさまざまな掃除アイテムやナチュラル素材が登場しており、用途や目的によって使い分けることもできます。コスパや効果を比較し、自分に合った方法を選んでみましょう。
クエン酸や他の消臭アイテムとの比較
| 掃除アイテム | 消臭効果 | コスト | 安全性 |
|---|---|---|---|
| 重曹 | ◎ | 安い | 高い(食品用可) |
| クエン酸 | ○ | 安い | 高い(食品用可) |
| 市販スプレー | ○ | やや高い | 香り付きに注意 |
クリーニングサービスへの依頼は必要か?
- ひどい汚れなどは専門業者に相談も検討。特にひどい汚れやペットの粗相によるシミが深く染み込んだ場合や、長年使用しているマットレスの蓄積汚れには、プロの手を借りることでしっかり対応できます。
- 料金は1万円〜2万円程度が相場ですが、サイズや汚れの状態によっては追加料金が発生することもあります。出張型のサービスを選べば、自宅で対応してもらえるのも便利です。
- 日常の掃除で予防しておくと安心。重曹やシーツのこまめな洗濯を取り入れることで、専門業者への依頼頻度を減らすことができます。
各方法の価格帯と選び方
| 方法 | 費用目安 |
|---|---|
| 重曹掃除 | 約50〜100円/回 |
| クエン酸・スプレー | 約100〜300円/回 |
| 業者クリーニング | 10,000円〜 |
重曹でマットレス掃除を行う際の注意点

重曹は便利ですが、素材や状況によっては注意も必要です。適切な方法で使えば安心ですが、間違った使い方をすると素材を傷めてしまう恐れもあります。正しい使い方で安全に掃除しましょう。
- メモリーフォームやウレタン製のマットレスは水分厳禁。水分を吸収しやすく、乾きにくいためカビや劣化の原因になります。
- 必ず取扱説明書を確認してから使用。メーカーが推奨する手入れ方法に従うことが、マットレスを長持ちさせるポイントです。
- 残った重曹は湿気を吸いやすいので密閉容器へ。湿気を含んだ重曹は効果が落ちやすくなるため、保存状態にも気をつけましょう。
- 使用したスプレーは冷暗所で保管。直射日光や高温多湿を避け、できれば密閉できる場所に保管するのが望ましいです。
- 重曹自体には殺虫効果はありませんが、湿気・皮脂を取り除くことでダニが繁殖しにくい環境をつくれます。防虫効果を期待するのではなく、あくまで予防目的として取り入れましょう。
まとめ

マットレスの掃除は面倒に思われがちですが、重曹があれば手軽に清潔を保つことが可能です。しかも特別な道具を揃える必要もなく、家にあるもので始められるのが魅力。毎日使うものだからこそ、日々のケアが快眠にもつながります。重曹を使った掃除を習慣にすることで、マットレスを長持ちさせることにもつながります。無理なくできる範囲で、まずは週1回のふりかけ掃除からはじめてみませんか?


