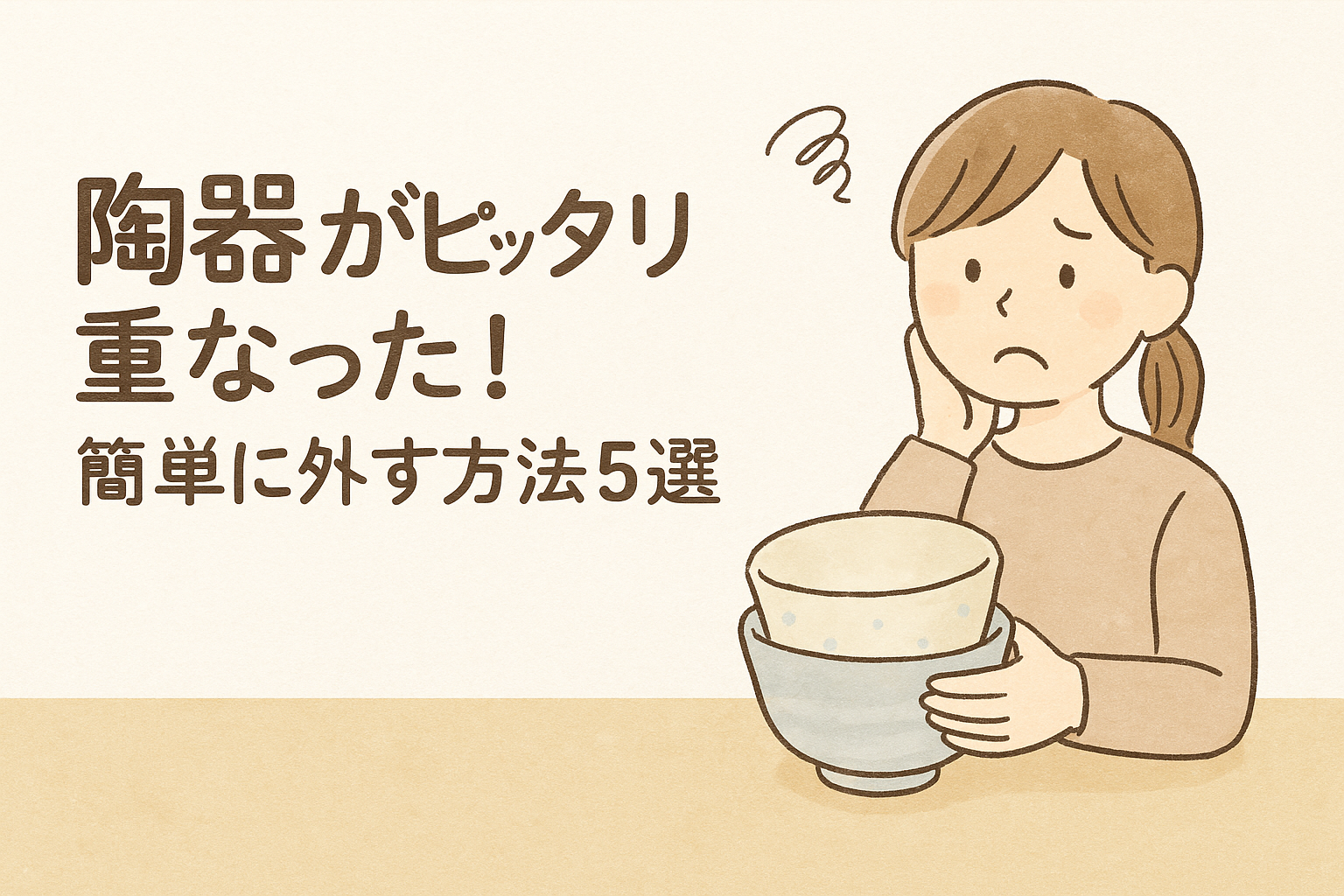お気に入りの陶器や食器を重ねて収納していたら、すっぽりとはまって取れなくなってしまった…そんな経験はありませんか? 無理に引っ張ると大切な器が割れてしまうかもしれないし、どうすればいいか途方に暮れてしまいますよね。そのまま放置すると、さらに固着して取り返しがつかなくなることも。でも、ご安心ください。
この記事では、はまってしまった陶器を安全かつ簡単に外すための効果的な方法を、原因の解説とともに詳しくご紹介します。もう大切な食器を諦める必要はありません。この記事を読んで、困った状況をスマートに解決しましょう!
陶器が外れないのはなぜ?原因を知ろう

陶器がピッタリと重なってしまうと、なぜこんなにも外れにくくなってしまうのでしょうか。その原因を知っておくことで、無理な力を加えずに対処するためのヒントが見えてきます。意外な理由が隠されていることもあり、正しい知識を持つことが安全に食器を外す第一歩となります。
陶器や食器が重なって取れない主な原因
陶器や食器が重なって取れなくなる主な原因は、物理的な摩擦と、次に説明する「真空状態」です。器の表面は一見滑らかに見えますが、実は目に見えない微細な凹凸があり、それが重なることで強い摩擦が生まれます。特に、釉薬(ゆうやく)のかかり具合や焼き物の種類によっては、この摩擦力が非常に大きくなることがあります。
また、洗った後によく水を切らずに重ねると、器と器の間に残った水分が糊のように作用し、より固着しやすくなります。さらに、器の形や重心のバランスが崩れた状態で重なると、外す際にさらに力を必要とし、割れるリスクを高めてしまうのです。
膨張や収縮による“真空状態”とは?
陶器がはまって取れなくなるもう一つの大きな原因は、物理的な現象である「真空状態」です。器がぴったりと重なると、内側の空間が密閉されます。この状態で温度が変化すると、外側と内側の空気に圧力差が生まれます。
たとえば、温かい状態で重なった器が冷めると、内側の空気が収縮し、気圧が下がります。これにより、外側の大気圧が器を強く押し付け、まるで吸盤のようにがっちりと固定されてしまうのです。この状態を「真空状態」と呼びます。この状態になっている場合、単に力任せに引っ張っても外れません。後述する冷却法や熱湯法は、この気圧差を解消して器を外すための効果的なアプローチです。
無理に外すと危険な理由
はまってしまった陶器を無理に外そうとすると、いくつかの危険が伴います。最も顕著なのが、器の破損です。陶器は衝撃に弱く、引っ張る際に無理な力が加わると、欠けたり、ヒビが入ったり、最悪の場合は真っ二つに割れてしまうことがあります。
また、勢いよく外れた反動で、床に落としてしまったり、手から滑り落ちて怪我をしたりする危険性も高まります。さらに、強い力で引っ張ると、器の縁が手に食い込み、思わぬ切り傷を負う可能性もゼロではありません。これらのリスクを避けるためにも、力任せに引っ張るのではなく、これから紹介する科学的なアプローチを試すことが大切です。
すっぽりはまった陶器を外す方法5選

ここでは、自宅で簡単に試せる、はまってしまった陶器を外すための5つの方法をご紹介します。どれも身近なものを使うので、特別な道具は必要ありません。あなたの状況に合わせて、最適な方法を試してみてください。
冷却法:氷水で縮ませて外す
この方法は、はまっている陶器の内側を冷やして縮ませ、外側の器との間に隙間を作ることで外すテクニックです。
- 内側にはまっている器に氷を入れ、その上から冷水を注ぎます。
- 外側の器はそのままにして、数分間待ちます。
- 内側の器が冷えて収縮したら、ゆっくりと持ち上げてみましょう。
※注意点:急激な温度変化は器を割る原因となるため、常温の器にいきなり氷を入れるのは避けましょう。また、外側の器は熱いお湯に浸けるなど、同時に温めるとさらに効果が高まります。
熱湯法:外側を膨張させて取る
こちらは冷却法と逆のアプローチで、外側の器を温めて膨張させ、内側の器との間に隙間を作る方法です。
- シンクや大きめのボウルに熱湯(熱すぎない程度)を張ります。
- 外側の器だけが浸かるように、はまった器をゆっくりと入れます。
- 数分間待ち、外側の器が温まったら取り出します。
- 外側の器が少し膨張して、内側の器がスッと抜けるようになります。
※注意点:急な温度変化は陶器を割る原因となります。熱湯すぎないお湯を使い、やけどに注意して行ってください。
洗剤やオイルで滑らせる裏技
摩擦が原因で取れなくなっている場合に有効な方法です。
- 器と器の隙間に食器用洗剤や食用油、ハンドソープなどを数滴たらします。
- 隙間に液体が流れ込むように、器を傾けたり、軽く揺らしたりします。
- 液体が全体に行き渡ったら、ゆっくりと回しながら引っ張ってみましょう。
※注意点:液体が滑り止めとなり、器を落としやすくなるため、タオルなどでしっかりと掴んで作業しましょう。また、洗剤は後でしっかりと洗い流してください。
内側から空気を入れるテクニック
この方法は、真空状態を解消するために有効です。
- 器の隙間に、ストローや細いチューブを差し込みます。
- 口でストローから息を吹き込み、内側の器に空気を送り込みます。
- 空気が入ると、内側の気圧が上がり、外側の器との圧力差が解消されます。
※注意点:あまり強く吹き込むと、器が勢いよく外れることがあるため、ゆっくりと慎重に行ってください。
薄いカードを差し込む方法
この方法は、わずかな隙間に物理的に空気を送り込むことを目的とします。
- キャッシュカードや名刺、トランプなど、薄くて丈夫なカードを用意します。
- 器のわずかな隙間にカードの角を差し込み、空気が入るように少しずつ動かします。
- カードを何枚か重ねて差し込むと、さらに効果的です。
※注意点:無理に力を加えるとカードが折れたり、器を傷つけたりする可能性があるので、少しずつ慎重に行ってください。
電子レンジを使うときの注意点

「電子レンジを使って温めたら外れるのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、電子レンジの使用には注意が必要です。使い方を間違えると、大切な器を壊してしまう原因となります。
陶器同士をレンジにかけて良い?
陶器同士がはまった状態で電子レンジにかけるのは、原則として避けるべきです。電子レンジはマイクロ波によって食品に含まれる水分を加熱しますが、陶器自体は直接温まりにくい性質があります。しかし、器の種類や釉薬によっては、急激な温度変化によってヒビが入ったり割れたりする危険性があります。
また、器の間に溜まった水分が急激に沸騰することで、器が飛び散るなどの思わぬ事故につながる可能性も否定できません。安全性を考えると、電子レンジの使用は推奨できません。
ガラスやプラスチックの場合との違い
ガラスやプラスチックの器がはまった場合も、電子レンジの使用は推奨できません。特にガラスは急激な温度変化に弱く、一気に加熱すると割れることがあります。耐熱ガラスでも、器の間に熱がこもることで破損するリスクが高まります。
プラスチックの場合は、熱で変形したり、有害物質が発生したりする可能性も考えられます。陶器同様、電子レンジの使用は避け、熱湯法や冷却法など、より安全な方法を試しましょう。
レンジ加熱時に避けるべきNG行為
電子レンジで器を温める際に避けるべきNG行為は以下の通りです。
- 空のまま加熱する:水分を含まない器を加熱すると、異常に高温になり、発火や破損の原因となります。
- 急激な加熱:一気に高温にすると、器にヒビが入る原因となります。
- 金属を含む器の使用:金彩や銀彩など、金属を含む装飾が施されている器は、火花を散らすため絶対に使用しないでください。
- 密閉状態での加熱:器がはまった状態は密閉に近い状態であり、内部の空気が膨張して破損するリスクが高まります。
これらのリスクを考慮すると、電子レンジは使わず、他の方法を試すのが賢明です。
鍋にはまったお皿を外す方法
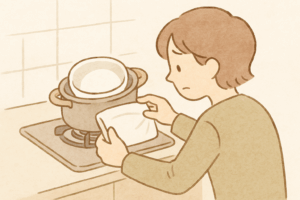
陶器だけでなく、鍋にお皿がはまってしまった場合も同様の対処法で解決できます。しかし、鍋の場合は深さや材質が異なるため、いくつかポイントがあります。
深皿と浅皿の重なりによる違い
深皿と浅皿が重なった場合は、深皿が外側となり、浅皿が内側にはまることがほとんどです。この場合、内側の浅皿を取り出すために、冷却法や洗剤法が効果的です。
特に鍋の場合、熱湯法は鍋全体を温める必要があり、量や熱効率の面で扱いにくいため、冷却法がおすすめです。浅皿に氷を入れて冷やし、鍋との間に隙間を作ることで、比較的簡単に取り出すことができます。
鍋・フライパンにピッタリはまった時のコツ
鍋やフライパンに陶器がはまってしまった場合は、冷却法と洗剤法を併用するのが効果的です。
- まず、内側にはまった陶器に氷水を入れて冷やします。
- 次に、陶器と鍋の隙間に洗剤やオイルを少量垂らします。
- 数分間待ち、陶器をゆっくりと回しながら持ち上げてみましょう。
これにより、陶器が収縮して隙間ができ、さらに洗剤の力で滑りやすくなるため、よりスムーズに外すことができます。鍋をひっくり返して振ったり、無理に引っ張ったりするのは、鍋や陶器を傷つける原因となるため避けましょう。
無理をせずに外すための安全な流れ
鍋やフライパンにはまったお皿を外す際は、まず冷静になることが大切です。
- 状況確認:はまり具合や、鍋・陶器の材質を確認します。
- 冷却法を試す:まずは氷水を使った冷却法を試します。最も安全かつ効果的な方法です。
- 洗剤法を併用:冷却法でうまくいかない場合は、洗剤やオイルを加えて滑りを良くします。
- 道具の使用:上記の方法でも外れない場合は、薄いヘラやカードを使い、わずかな隙間に差し込んでみましょう。
もし、何度試しても外れない場合は、無理をせずに専門家に相談することも検討しましょう。大切な器や鍋を傷つけないことが何よりも重要です。
再発防止のためにできること

一度はまってしまうと、取り出すのに苦労しますよね。二度と同じような状況にならないために、日頃からできる工夫をいくつかご紹介します。少しの気遣いで、大切な食器を守ることができます。
食器を重ねるときの工夫
食器を重ねる際には、以下の工夫をすることで、はまり込みを防ぐことができます。
| 工夫のポイント | 具体的な方法 |
|---|---|
| しっかりと乾燥させる | 洗った後は完全に水気を拭き取ってから重ねる。 |
| 間に布やペーパーを挟む | フェルト製のクッションシートやキッチンペーパーを器と器の間に挟む。 |
| 重ねすぎない | 一度に重ねる枚数を減らし、器に負担をかけないようにする。 |
| サイズを揃える | 同じサイズや形状の器同士を重ねる。 |
これらのちょっとした工夫で、摩擦や湿気による固着を未然に防ぐことができます。
キッチン収納の見直しポイント
はまり込みを根本的に解決するためには、キッチン収納全体を見直すことも有効です。
- 立てて収納する:お皿スタンドなどを活用し、お皿を立てて収納することで、重ねる必要がなくなります。
- 仕切りを活用する:収納ケースや仕切り板を使って、器がずれたり重なったりするのを防ぎます。
- 使用頻度で分ける:よく使う器は手前に、あまり使わない器は奥に置くなど、整理整頓することで、重ねておく時間を減らすことができます。
- デッドスペースを活用:食器棚の隙間や引き出しに、はまり込みやすい小皿などを個別に収納するスペースを確保する。
収納方法を見直すことで、器がはまってしまうストレスから解放されるだけでなく、キッチンの使い勝手も向上します。
まとめ:陶器がはまった時の正しい対処法

陶器がピッタリはまってしまった時は、焦らず、正しい方法で対処することが何よりも大切です。
- まずは原因を知る:摩擦や真空状態が原因であることを理解し、力任せに引っ張らない。
- 温度差を利用する:「冷却法」や「熱湯法」で器の膨張・収縮を促し、隙間を作る。
- 滑りを良くする:「洗剤やオイル」を使って、摩擦を減らす。
- 空気を送り込む:ストローやカードで「真空状態」を解消する。
- 無理をしない:もしうまくいかなくても、無理に力を加えるのはNG。大切な器を傷つけないことを最優先に。
日頃から食器を丁寧に扱い、収納方法を工夫することで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。もし、また同じような状況になったら、この記事を思い出して、落ち着いて対処してくださいね。